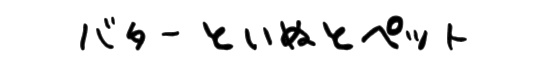
2004-01-09
_ ペンギン村にギャングたち
大船駅で、本当に高橋源一郎とすれ違った。以前は「見ただけでどうってこともないだろう」と予想していたわけだけど、実際に見てみたら意外なほどうれしくて、ちょっとドキドキした。『さようなら、ギャングたち』と、「メイキング・オブ・同時多発エロ」の連載を何回か群像で読んだくらいだけど。
田中邦衛とすれ違ったときより興奮した。
その直後、電車の中で読んでいたポール・オースター『ムーン・パレス』から。古本屋で『幽霊たち』を手に取ったとき、高橋源一郎の帯文がなかったら僕はオースターを読んでいなかったかもしれない。
こういう道化じみた物言いが、ますます僕の典型的言動になってきていた。完璧にまっとうな質問に対して、言い逃れや、論理のすり替えや、詭弁をもって応じるのである。自分の窮状を内緒にしておこうとすれば、嘘を並べて追及をかわすほかなかった。貧乏のどん底に落ちていけばいくほど、捏造する話もどんどん奇怪で歪んだものになっていった。禁煙した理由、酒を断った理由、外食をやめた理由——何であれ、何か途方もない論理に基づく説明を僕は造作なくひねり出した。いまや僕の口調たるや、アナーキストの隠者、世捨て人の現代版、十九世紀の
機械破壊運動家 の再来という趣だった。でもとにかく友人たちは面白がったし、僕も僕で首尾よく秘密を守り通せた。もちろん、こんなペテンじみたふるまいには、自尊心も大きく作用していたにちがいない。でも、いちばん大事な点は、自分で下した決断に関して、誰からも干渉されたくなかったということだ。その決断を話して聞かせれば、きっと相手は哀れに思ってくれただろう。ひょっとしたら援助を申し出てくれたかもしれない。そうなるとすべては台なしになってしまう。それよりは、みずから築き上げた錯乱のなかに自分をとじ込めて、とことん道化を演じきるほうがいい。そして時が尽きるのを待つのだ。(文庫版44-45頁)
そして時が尽きるのを待つのだ。
