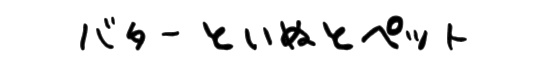
2003-06-23
_ 大塚英志『キャラクター小説の作り方』(講談社現代新書)
4061496468僕はここしばらく、日記での一人称を意図的に「僕」にしてきた。しかも僕が「僕」と言うとき、それは間違いなく村上春樹の影響下にある。「僕」を使って日記を書いている今日のこの日記も、また同じである。ある時期までは、村上的な文脈を読みとられるのがいやだったので、意図的に「僕」を避けて他の一人称を使っていたのだが、今度は意図的にそれを解禁した。
なぜそうなのかといえば、僕がいま陥っている(と自分で思っている)私的な状況が、村上の小説に多く描かれているような状況に近いと、またその表象の作法に従って表現することがふさわしい(≒都合がよい)と、さらにいえば僕にとって救いになると感じているからだ。
Web上で発表されている日記は、日記といえども多様であり、仮構を含む程度にもばらつきがある。日記を含む上位カテゴリとしての「テキスト系」に分類されるものまで含めれば、まったくの仮構であるものからほとんど仮構を含まないものまで見つけることができる。『キャラクター小説の作り方』にしたがって述べるなら、「キャラクター小説」に近い極から「私小説」を越えて「ノンフィクション」に近い極まで、全てそろっていると言える。僕が書いているものをこの直線上に位置づけるとすれば、フィクションでもノンフィクションでもない「私小説」とするのが適切だと思う。
大塚は本書の最後で次のように述べる。
あるいは「私小説」の「私」もまた仮構に過ぎないことは多くの私小説家自身が語っているし、多くの文学研究も同様に指摘しています。
(302頁)
僕が「僕」という一人称を使うとき、僕が描く「僕」の仮構性をはっきりと自覚していた、とまでは言わない。だがうっすらと感じていたのは確かだし、同時に見ないふりをしていたのも確かだ。僕は「僕」でありたかったし、必要でもあった。今もまだ「僕」を使って日記を書いている。僕はそうして村上春樹のような世界に僕を置き、自分自身を「現実だと述べている仮構」の中に置いてキツさをやりすごそうとしている。
大塚英志は、「『仮構の私』をあることに」することそのものを否定しているわけではない。小説を書くときにはどうしても仮構を含まざるを得ず、「キャラクター小説」と「私小説」とは地続きで、分類そのものが難しいと言っているだけだ。ただ、そのことに無自覚でいることを批判しているのである。
ぼくはキャラクター小説を「作者としての私」ではなく『キャラクターとしての私」を自覚的に描く小説だ、と記しました。それは多くの文芸史的「文学」が「文学」に「私」を保証してもらっていることに無自覚なことへの逆説と指定されています。つまり「文学」が、「私」という存在がその起源において「キャラクター」であったことに無自覚な小説として今、あり得るのなら、キャラクター小説は「私」が「キャラクター」としてあることを自覚することで、いっそ「文学」になってしまいなさい、とぼくは主張することで、この小説講座を終えようと思っていることは、すでにお解りだと思います。
(303頁)
こう言われることで、僕は僕自身の日記の仮構性をはっきりと自覚した。したくもなかったのだが、させられてしまった。しかしその行為を否定されたわけではないし、たとえ否定されたとしても自分で否定するつもりはない。そもそも「私小説」は仮構を含んでいたのだし、また完全に仮構だったわけでもない。それは「キャラクター小説」でさえもまた同じである。
僕は僕自身の日記を「文学」だなどと言いたいのではないし、Web日記や「テキスト系」を「文学」としたいわけでもない*1。同時に、「文学」についてもそれほど大仰なものだと捉えているわけでもない——だから、大塚に共感できる点はとても多い。
仮構しか描けない、と自覚することをもって、初めて描きうる「現実」があるのです。とうに「現実」と向かい合うことを止めた多くの文芸誌的「文学」の真似をする必要は全くありません。
僕は、大塚が「キャラクター小説」に可能性を見出すのと同じ意味で、Web日記にも可能性を感じている。その仮構性を自覚した上でもがいてみるなら、現実に対してはたらきかけることができるし、少なくとも自分がそうするためのきっかけにはなりうると考えている。
大塚は、手塚治虫や戦後まんが史の功績を、死なない身体を持つ「記号的」なキャラクターを用いて生身の人間を、死にゆく身体を描こうとした努力にあるとしている。実現したかどうかはわからないが、まんがはそれを求めたのだ。僕は手塚治虫になれるかどうかわからないが、「記号的」表現を用いながら「記号的」表現の外に向かってもがきつづけたその気概だけは、見習いたいと思う。
*1 ただ、日本文学のルーツに日記という形式が大きく関わっていることには、多くの人が気づいていると思う。しかも紀貫之が女性に自らを仮託した『土佐日記』に顕著なように、日本の日記は仮構性を含んでもいた。これはこれで追う価値のあるテーマだと思う。
_ 僕ぼく私わたし俺おれ己
ただ、村上春樹的な文脈上にある「僕」を使いつづけることについては躊躇がある。特に限定的な意味での、つまり世界と向かい合うのを避けているという意味での「僕」を使いつづけることはためらってしまう。
以前「俺」を使っていたのだが、これもしっくりきていたわけではなかった。どうにも野性的なイメージが強く、消極的なことを書いていてもワイルドに突き進んでいるような先入観が混じるように思えたからだ。また、日本語の利点を活かしてなるべく一人称を出さずに書いてみたりもしたのだが、これも窮屈だった。やはり一人称は使いたい。
日本語の一人称*1には、多かれ少なかれ上下関係や慣れ親しみの度合いを示す意味がつきまとっている。「僕」は相手よりも自分を下に置く意味を含むんでいる。「私」は上下関係の面でニュートラルに近いが、他人行儀にすぎる気がする。こういった関係から自由になるために、あまり使われていない≒手垢のついていない語、たとえば「己」と書いて「おれ」と読むようなことも考えた。だが、使い慣れないだけにやはり違和感が残ってしまう。
村上を抜きにしても、「僕」という語はそれなりにしっくり来る。もちろん「僕」を使っている人は村上だけではなく、むしろ圧倒的にそれ以外のほうが多いわけで、それほど気にすることではないのかもしれない。
他によい選択肢はないし、今はそういう気分だし、もう少しこのまま「僕」を使ってみよう。
*1 英語の I などはそういったことから自由なのかもしれないが、ほかに選択肢がないという意味では窮屈なのかもしれない。
